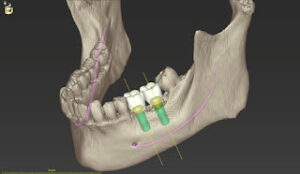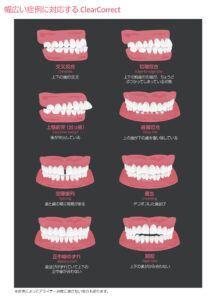入れ歯(義歯)は、失った歯を補うための取り外し可能な人工歯のことを指します。
入れ歯の主なメリットとデメリットをまとめると
メリット
1. **経済的**:
– 入れ歯はインプラントやブリッジに比べて一般的にコストが低く、経済的負担が軽いことが多いです。
2. **取り外し可能**:
– 入れ歯は取り外しが可能なため、清掃がしやすく、口腔衛生を保ちやすいです。
3. **手術不要**:
– インプラントのような外科的手術が必要なく、比較的簡単に装着できます。
4. **複数の歯を一度に補う**:
– 多数の歯を失った場合でも、一つの入れ歯で一度に複数の歯を補うことができます。
5. **即時対応**:
– 一時的な措置としてすぐに使用できる即時義歯もあり、特に急ぎの場合に便利です。
デメリット
1. **安定性の問題**:
– 入れ歯はインプラントや固定ブリッジと比べて動きやすく、噛む力が大きく劣ります。装着感に慣れるまで時間がかかることもあります。
2. **適応期間**:
– 初めて入れ歯を装着する際は、慣れるまでの適応期間が必要です。違和感や痛みを感じることもあります。
3. **定期的な調整が必要**:
– 顎骨の変化により、定期的に入れ歯の調整が必要となります。長期間使用するためには、定期的なメンテナンスが重要です。
4. **食事の制約**:
– 硬い食べ物や粘り気のある食べ物を避ける必要がある場合があります。また、噛む力が自然歯に比べて弱くなることがあります。
5. **見た目と発音**:
– 入れ歯の見た目が自然歯と完全に一致しない場合があります。また、装着初期には発音が不明瞭になることもあります。
以上まとめると
入れ歯は、多くの歯を失った場合に有効な選択肢であり、比較的低コストでありながら、見た目や機能をある程度回復させることができます。
研究学園歯科ではノンクラスプデンチャーという審美性のたかい入れ歯やたわみにくく薄くつくれる
コバルトクロム床の義歯も可能です(保険適用外)
入れ歯を検討する際は歯科医師とよく相談し、自分に最適な治療方法を選ぶことが重要です。